「わからないことがあったら聞いて」
「わからないことがあったら聞いて」と伝えたのに、部下から質問が来ない。または、些細なことまで全部聞いてきて自分の時間が奪われる…そんな経験はありませんか?
実は、この「わからないことがあったら聞いて」という何気ない一言が、部下の成長を止めている可能性があります
本記事では、10年以上のマネジメント経験から導き出した「本当に部下が育つ言い方」を、すぐに使えるフレーズ集と共にご紹介します。
この記事でわかること
- なぜ「わからないことがあったら聞いて」がNGなのか
- 新人が質問できない心理的背景
- 今日から使える効果的なフレーズ50選【シーン別】
- 質問しやすい職場環境の作り方
- 部下の主体性を引き出す指示の出し方
「わからないことがあったら聞いて」がダメな3つの理由

理由1:相手の思考を停止させてしまう
「わからないことがあったら聞いて」と言われた新入社員や若手社員は、次のような心理状態に陥ります。
- 何がわからないかが、わからない
- どう質問すればいいのか、わからない
- 上司が忙しそうで聞けない・気まずい
- 「こんなことも知らないの?」と思われたくない
結果: 質問できずに仕事が止まるか、些細なことまで全部聞いてくるかの両極端になります。
理由2:相手の考える機会を奪い、主体性を失わせる
「わからないことがあったら聞いて」は、一見親切に見えて実は相手の思考力と自主性を奪う指示です。
- 少しでもわからないことがあれば、すぐに質問してくる
- 自分で調べる習慣がつかない
- 将来的に「指示待ち人間」になってしまう
- 上司の時間が細かい質問対応で奪われる
理由3:心理的安全性が確保できず、報連相が機能しない
「わからないことがあったら聞いて」という指示は、どこまでが相手の責任で、どこからが自分の責任なのか境界が不明確です。
- 質問しやすい環境になっていない
- 報連相(ほうれんそう)が機能しない
- フィードバックの機会を失う
新入社員が質問できない・聞いてこない心理とは
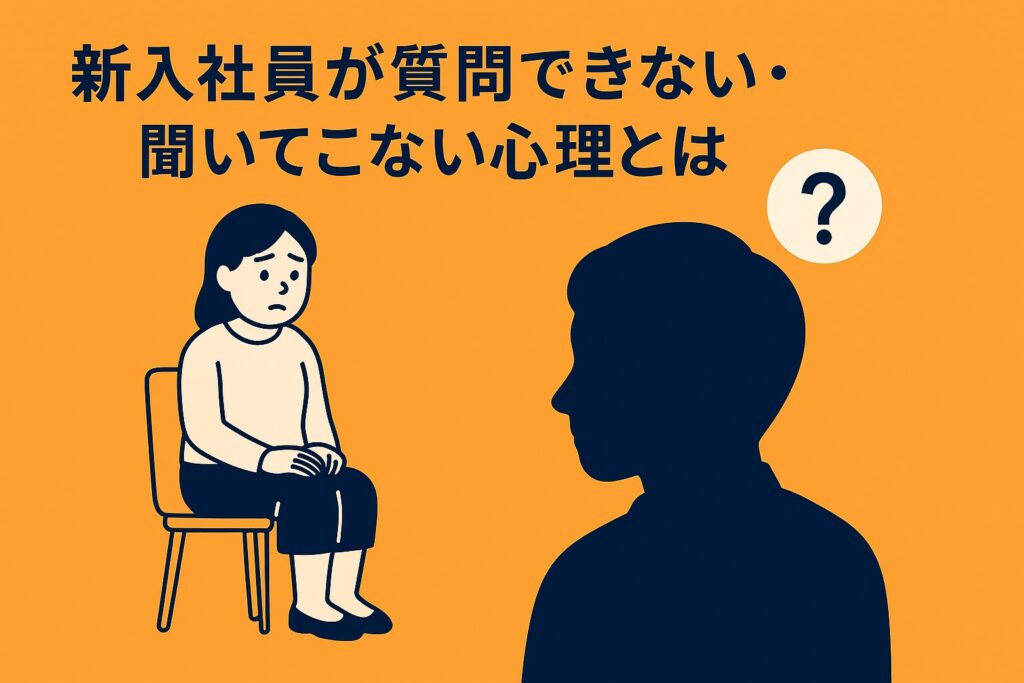
なぜ新人は「質問できない」のか?
部下が質問してこない背景には、以下のような心理が隠れています。
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 質問の仕方がわからない | 5W2Hで整理できない、何を聞けばいいのかわからない、上手な質問の仕方を教わっていない |
| プレッシャー | 「そんなことも知らないの?」と言われた経験、「自分で調べなさい」と突き放された記憶、罪悪感 |
| 上司が怖い | 上司が忙しそう、機嫌が悪そう、過去に怒られた経験がトラウマ |
| 全体像が見えない | 何がわからないかわからない、専門用語が理解できない、どこから手をつければいいかわからない |
「わからないことがあったら聞いて」の代わりに使うべきフレーズ集【言い換え・別の言い方】

「わからないことがあったら聞いて」の代わりに使うべき、具体的で実践的なフレーズをシーン別にご紹介します。
パターン1:新規業務・プロジェクトを任せる場合
ポイント: プロセス自体を考えてもらう
| ❌ NG | この資料作っておいて。わからないことがあったら聞いて。 |
| ✓ OK | どのように進めるか、いくつか案を考えて明日の午前中までに報告してもらえますか? |
効果的なフレーズ例:
- まずはプロセス案を3つほど作ってもらって、それを一緒に確認させてください
- ○日までにアプローチ方法の案を考えて、相談してもらえますか?
- この業務のゴールは○○です。そこに向けてどう進めるか、あなたのアイデアを聞かせてください
- 過去の事例を3つ共有するので、それを参考に自分なりのやり方を考えてみてください
パターン2:マニュアル・OJTがある場合
ポイント: 「自分で解釈する」ステップを挟む
| ❌ NG | マニュアル見ておいて。わからないことがあったら聞いて。 |
| ✓ OK | マニュアルを確認して、実際にやってみる前に、自分なりの理解を一度説明してもらえますか? |
効果的なフレーズ例:
- この業務の目的は○○なので、プロセスで不明点があれば、あなたならどう対応するか案を考えて相談してください
- 手順書を読んで、「ここは曖昧だな」と思った箇所をリストアップしてください。その上で、あなたならどう判断するか教えてください
- まずは一通りやってみて、つまずいた箇所を5W2Hで整理してから相談してください
- この作業の目的とゴールを理解していますか? それを踏まえて、どう進めるか説明してみてください
パターン3:中間報告のタイミングを明確にする
ポイント: 定期的なチェックポイントを設ける
| ❌ NG | 進めておいて。わからないことがあったら聞いて。 |
| ✓ OK | 作業の30%まで進んだら、一度方向性を確認させてください |
効果的なフレーズ例:
- 明日の15時に30分時間を取るので、そこまでの進捗と疑問点を整理しておいてください
- 最初の○○の部分ができたら、まず見せてください。残りはそれを確認してから進めましょう
- 毎日17時に10分間、進捗報告の時間を作ります。そこで困っていることを共有してください
- 週1回の1on1で、疑問点をまとめて相談してもらえますか?
パターン4:質問の型を教える
質問の仕方を具体的に教えることで、部下の質問力が向上します。
質問の型(テンプレート)
- 【現状】何について困っているか(5W2Hで整理)
- 【調査】自分で調べたこと・試したこと
- 【案】自分なりの解決案(複数案)
- 【判断】それぞれのメリット・デメリット
- 【相談】どの案が良いと思うか、なぜそう思うか
心理的安全性の高い、質問しやすい職場環境の作り方
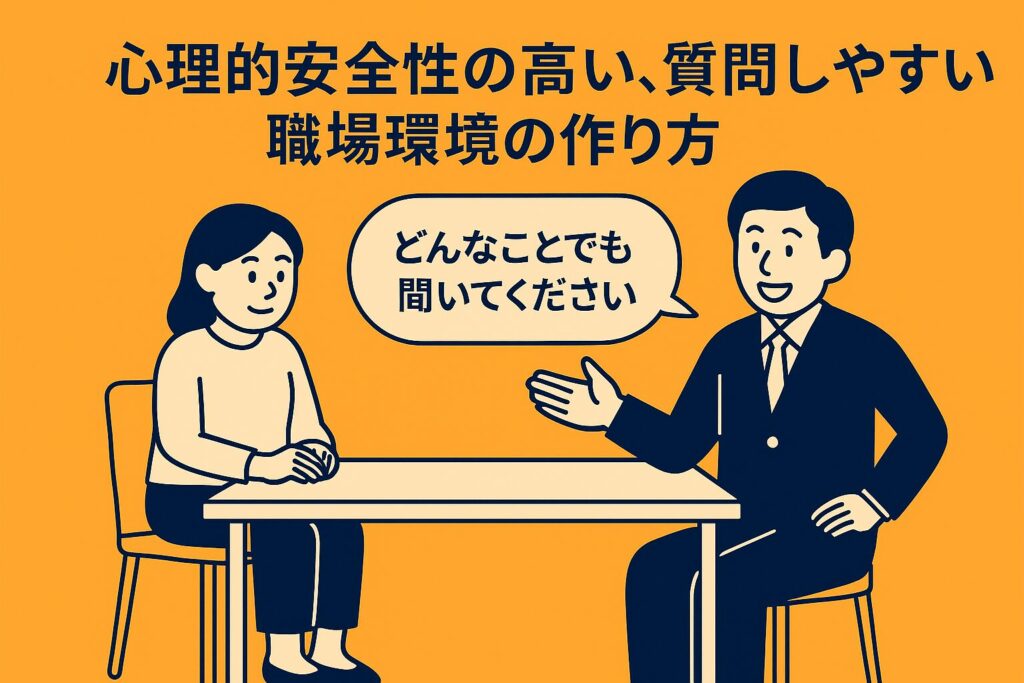
心理的安全性の高い、質問しやすい環境を作る5つのポイントをご紹介します。
定期的な1on1の実施
- 週1回、30分の1on1を設定
- 業務の進捗だけでなく、悩みや不安も聞く
- 「最近困っていることはある?」と具体的に聞く
「聞いてくれてありがとう」文化の醸成
- 質問されたら「いい質問だね」と肯定する
- 「聞いてくれて助かった」と感謝を伝える
- 質問しなかったことを責めない
オープンな質問の奨励
- 定例会議で「質問タイム」を設ける
- Slackやチャットで質問専用チャンネルを作る
- 「こんなこと聞いていいのかな」を無くす
失敗を許容する文化
- 「失敗は成長のチャンス」と伝える
- 自分の失敗談を共有する
- 完璧主義を求めない
忙しさを見せない工夫
- 「今は手が離せないので、15時に相談しよう」と代替案を提示
- 相談可能な時間帯をカレンダーに明示
- 表情や態度に気をつける
よくある質問(FAQ)

Q1:それでも質問が多すぎる場合はどうすればいい?
A:質問の「型」を教え、考える習慣をつけましょう。
上記の質問テンプレートを使うことで、相手は質問前に自分で考える習慣がつき、問題解決能力が向上します。
Q2:本当に基礎知識がない新入社員にはどうすればいい?
A:最初に「学習期間」を設け、段階的に教えましょう。
- まずは3日間でこの資料を読み込んで、要点をまとめてください
- その後、わからなかった箇所を一緒に確認しましょう
- 理解度を確認しながら、徐々に実践に移行します
Q3:「気軽に聞いて」「遠慮なく聞いて」もNGなの?
A:はい、同じ理由でNGです。代わりに具体的な相談方法を伝えましょう。
例:「毎朝10時に進捗確認するので、そこで相談してね」最初に「学習期間」を設け、段階的に教えましょう(OJTのコツ)。
まとめ:今日から実践できること
今日からできるアクションリスト
- 「わからないことがあったら聞いて」を今日から使わない
- 指示を出す際は、必ず「チェックポイント」を設定する
- 相手に「考える範囲」を明確に伝える
- 業務の「目的」を必ず共有する
- 質問しやすい具体的な環境を作る
- 質問の型を教え、質問力を向上させる
- 定期的な1on1やフィードバックの機会を設ける
「わからないことがあったら聞いて」は、一見親切ですが、実は相手の可能性を制限する言葉です。
相手に考えてもらう言い方を心がけることで、新入社員・若手社員の成長速度が上がり、主体性が育ち、あなたの負担も減ります。
今日から、適切な範囲で任せる効果的なマネジメントを実践していきましょう。
💡 この記事が役に立ったら
 Todd
Toddぜひチームで共有して、一緒に実践してみてください
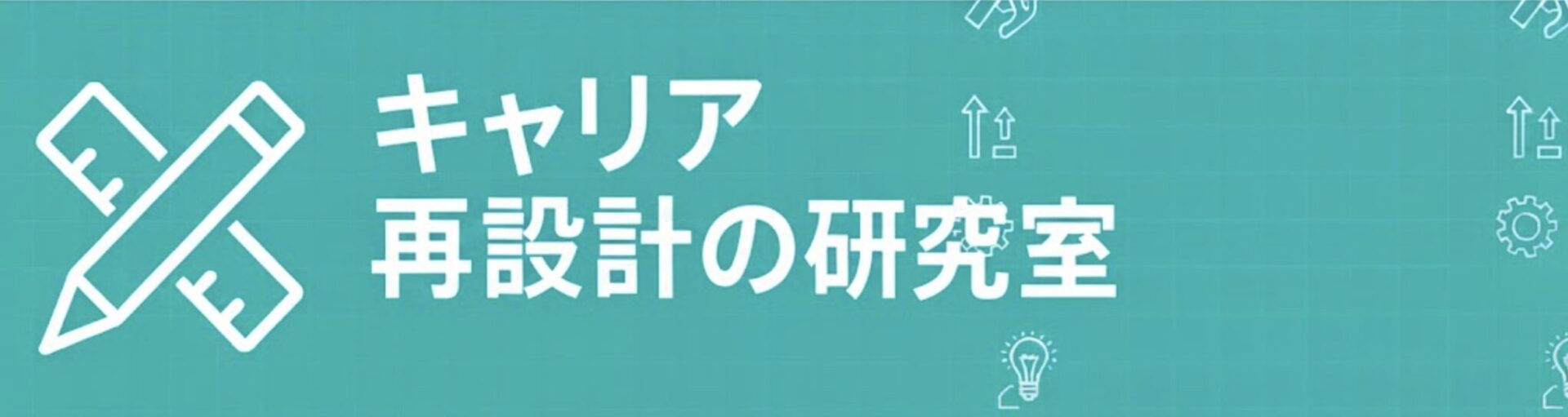
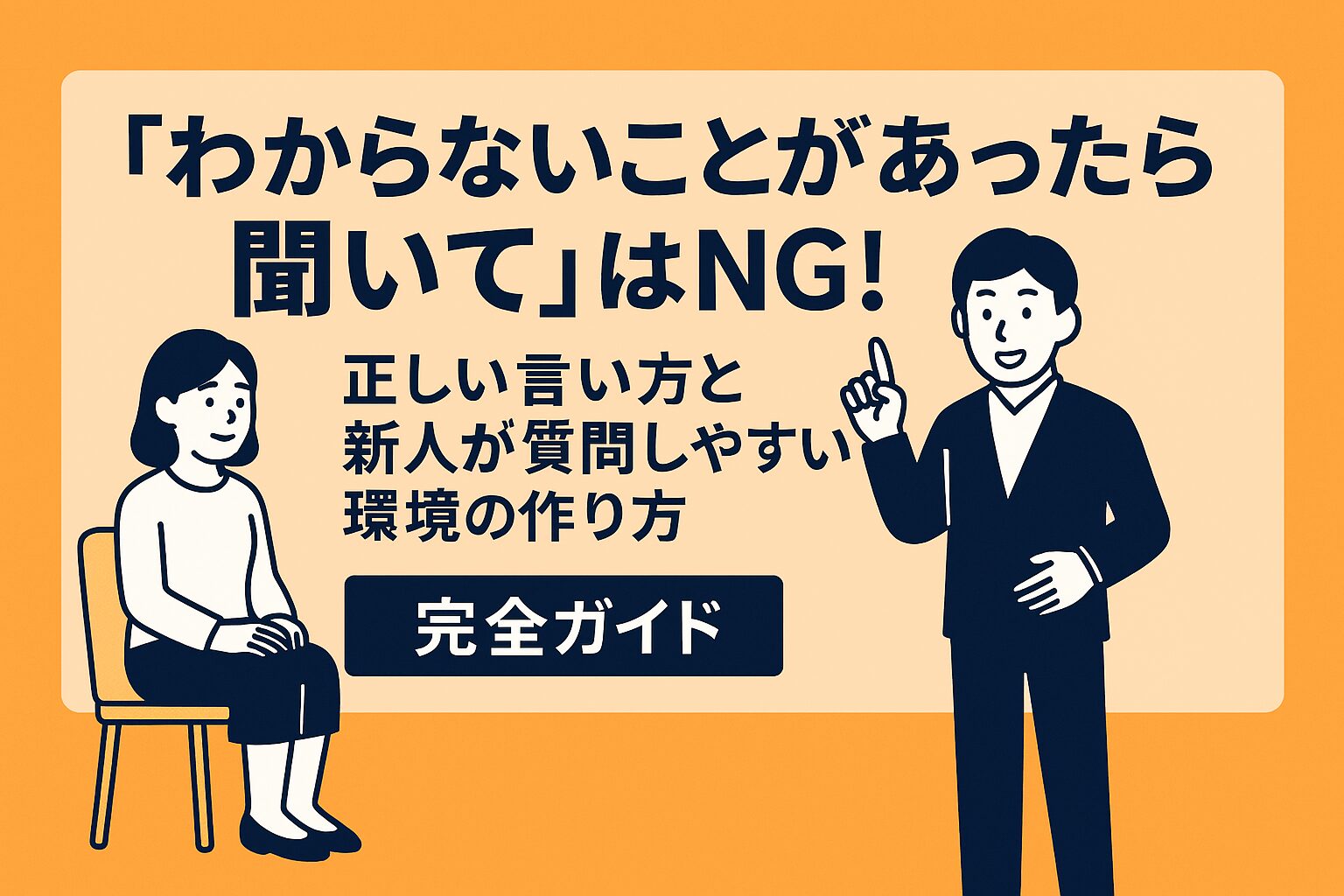
コメント